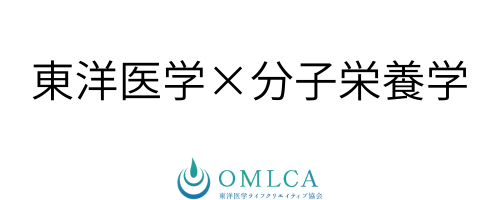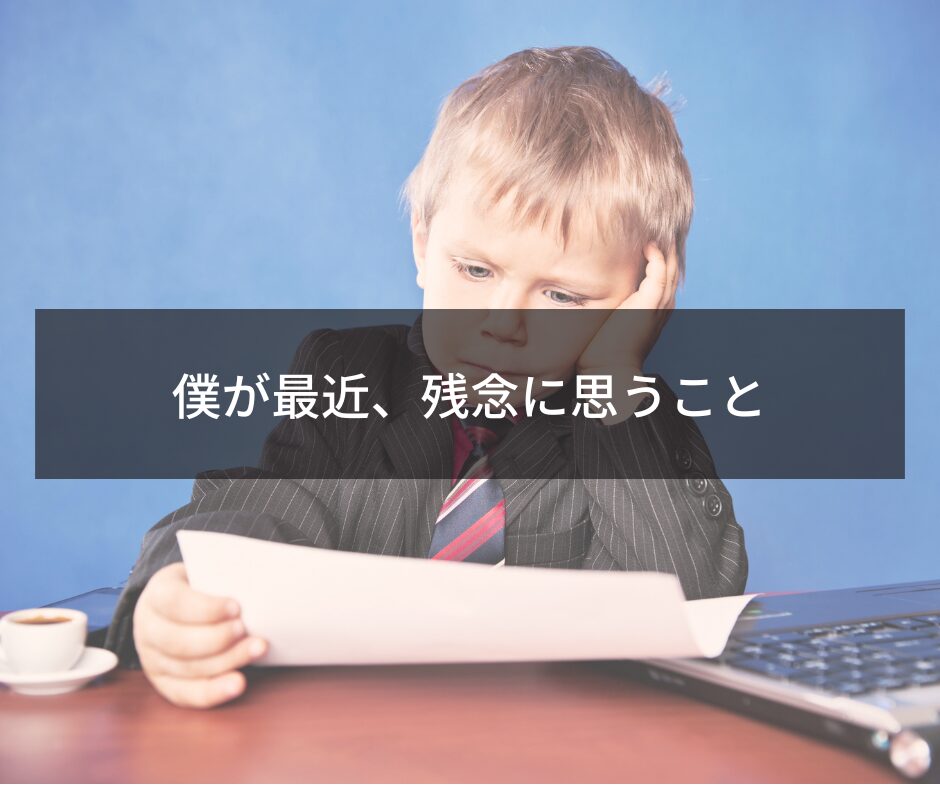ちょっと突然ですが、僕の父のことについて少し書きながら、今後自分がやっていくべきことについて考えてみたいと思います。
父も鍼灸師でした。 というより、私は父の影響を受けて鍼灸の道に入ったんです。
まずはそんな父のことについて少し書いていきます。
父、島田隆司について
僕の父は、68歳で亡くなりました。
日本伝統鍼灸学会の会長在職中のことでした。
自分が今年66歳になることを考えると、ちょっと複雑な気分になります。
私にとって父は、常にはるか前を歩いている鍼灸の師匠であり、とても尊敬できる父親であり、温かい家族でしたから…。
1999年12月、弟の結婚式の前日に「お父さんの調子が悪いからすぐ来てちょうだい」と母に呼ばれて実家へ行くと、黄疸で身体中が真っ黄色になっていました。
結婚式にはどうしても出ると言い張るので、鍼灸の治療をして、結婚式の後には必ずすぐに病院を受診するよう伝えて帰りました。 翌日すぐに入院となり、検査の結果を聞きに行った母と私に主治医はこう言いました。
「ご主人はもうご自分ががんで余命が半年だということをご存知で、奥様やご家族にそのことをどう伝えたらいいか悩んでいらっしゃいますよ」。
涙がいつまでも止まらなかったのを覚えています。
胆管がんでした。
その後の入退院の間、鍼灸界の有名な先生方が連日のように治療に来てくれました。
もちろん僕も週に3〜4回はなんとか時間を作って実家に治療に通いました。
父はそういった治療の甲斐もあってか、がんが縮小傾向になり、もしかすると手術で取れるかもしれないという状態にまでなりました。
本人も、自分が人生をかけて進む決心をした大好きな鍼灸によって改善傾向にあることを聞いて、とても嬉しそうにしていました。
精密検査のために癌研病院に入院することになり、その前に移った病院で鍼灸治療(特にお灸)を禁じられ、最終的にやはり切除は難しいとの判断が下されてしまいました。
亡くなったのは、2000年の8月10日です。
もう25年近くが経ってしまいました。
残念に思うこと
もちろんいまなら、栄養や食事を使ってできることがいろいろあります。
がんの栄養療法についての研究は結構進んでいて、がんの幹細胞に対してどのような栄養素が効果的なのかを詳細に調べる検査方法まであったりします。
栄養と鍼灸を併せて使うことで、効果はさらに上がることも僕自信実感しています。
ただそれよりも、がんにならないために栄養療法と鍼灸でしてあげられたことがいろいろとあったはずだと、いまなら考えられます。
がんになるにはそれなりに理由があります。
そのなかには栄養の過不足、大きなストレス、運動不足なども含まれています。
がんになった後に栄養カウンセリングを受けに来られる方も結構いるんですが、そんな方にはまず最初に「どうしてがんになったと思いますか?」と聞くことにしています。
皆さん、自分なりに思い当たることがいろいろとあるようです。
そう、がんを手術で切除できたり、化学療法で縮小して寛解したとしても、それで終わりではないんです。 「なぜがんになったのか」を突き止めて、その根本的な原因を改善しなければ、またがんになります。
僕がいつも言っているのは、そういうことです。
だから、がんになった患者さんに対しては、一緒にがんになった原因を考えることから始めるようにしています。
それが、再発しないためにいちばん大事なことだと信じているからです。
遺伝と体質
父のことを考えたついでに、その人の子供としての自分のことも考えてみることにします。
父はけっして身体が強かったわけではないんです。
僕がまだ小学校に上がる前には、まだサラリーマンだった父は、肝臓を悪くして入退院を繰り返していました。
そのときに図書館で出会った本に導かれて断食道場に入り、断食と鍼灸、温冷浴などによって体調を回復し、会社をやめて鍼灸の世界に飛び込んだんですから。
それから母も、僕の出産当時はかなり痩せていたので、僕自身は先天の精は不足しがちで生まれてきたんだと想像することができます。
母は糖尿病でもありましたから、その影響も遺伝的要素として僕の遺伝子に伝わっているかもしれなくて、血糖コントロールが得意ではないのはそのせいかもしれないです。
皆さんも、そんなふうに自分の遺伝的な素因を両親の健康状態などから推測してみると良いかもしれません。 それがある意味で「体質」だと思い込んでいる場合も多いように感じます。
でも遺伝ですべてが決まるわけではないのは、いつも書いている通りです。
そういう意味でも、僕自身が後天の精のメインである栄養を適切に補充して、健康で楽しく長生きできるようにして、自分の身体をもって分子栄養学の良さを証明していきたいと思っています。
自分が両親からどんな体質を受け継いでいるのかを知った上で、栄養療法でそこを補っていけらた、まさに東洋医学の考え方と合致するわけですよね。
僕が伝承医学としての東洋医学にプラスしてできることは、そういうことかもしれないと最近強く感じています。
今回はこの辺で。
3/2(日)まで「分子栄養学無料オンライン勉強会」のお申込みを受け付けていますので、興味のある方は下のボタンからどうぞ。