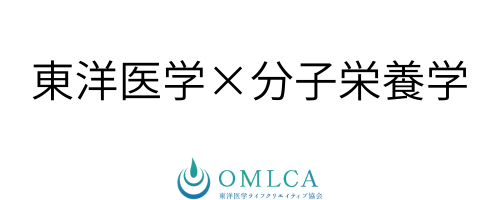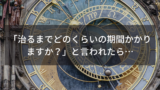よく「分子栄養学を鍼灸の臨床とどう結びつけて使っているんですか」という質問をいただきます。
それは内緒です(笑)などと言っていては、僕が広めたいと思っている正しい栄養療法が浸透しないので、公開することにします!
うまく伝わるといいんですけど…。
そうそう、「分子栄養学無料勉強会」のお申し込みフォームができました。
お申し込みの受付は2/17(月)からになります。
メルマガに登録いただいている方には、メールでご案内をお送りしますので、興味のある方はぜひご参加ください。
メルマガ登録がまだの方は、こちらから。
全体の流れ
まずは全体の流れを簡単に示します。
- 1週間分の食事記録・血液検査結果を提出してもらう
- 食事内容をチェックする
- 血液データをチェックする
- 一般的な問診をする
- 食事・血液データの問題点についての追加問診をする
- 体表所見、舌・脈所見を取る
- 上記を総合して分子栄養学的な根本原因を類推する
- 確認のための追加問診をする
- 食事・栄養アドバイスをする
以上が大まかな流れになります。
もう少し詳しく説明を加えますね。
食事記録のチェック
初診では、1週間分の食事記録を出してもらって、これをチェックします。
まず、いちばん大事な三大栄養素のバランスをチェックします。
PFCバランスがおかしいに場合などは、それに対して追加で質問をします。
例えば「お肉をあまり食べていないけど、その理由は何ですか?」 。
答え「お肉を食べると胃がもたれるんです」。
ここから分かることを類推するための質問をさらに追加します。
例えば胃が弱い、胃酸の出が悪い可能性があれば、まずピロリ菌の有無をチェックします。
また、次のような質問を追加することもあります。
胃薬をよく飲みますか?
お肉を食べた後に便が少し黒かったり臭かったりしませんか?
お魚なら食べられますか?
さらに、食事内容から三大栄養素以外に不足している栄養素がないかを類推します。
例えば野菜をほとんど摂っていなかったり、外食ばかりだった場合もその理由を追加して尋ねます。
血液データのチェック
できるだけ事前に血液データをもらって、これを分子栄養学的な基準でチェックします。
標準医療の基準値は,病気を見つけたり治したりするためなので、栄養学的な基準はかなり厳しめになります。
分子栄養学的な理想値とかけ離れた項目がないかをチェックし、あれば想定される問題点や症状の有無を確認します。
例えば空腹時血糖値や中性脂肪が低ければ、「低血糖」を起こしている可能性があると考え、その場合は低血糖の症状がないかを追加で質問します。
特に夜間低血糖がないかは重要なので、睡眠の質、中途覚醒や寝汗、歯軋りや食いしばりの有無、起床時の首肩こりや倦怠感などについて尋ねます。
問診内容は、問題があればあるほど微に入り細にわたることになります。
医療面接をカリキュラムに入れるキッカケをつくったものとしては、「どうなんだろう」と自問自答しながら、根本原因を求めて、ひたすら問診をしまくります(笑)
問診以外の四診をチェック
特に食事記録や血液データで問題がありそうな項目に関連した体表所見をチェックしていきます。
例えばタンパク質不足や貧血がある場合、下腿に青タンがないか、髪の毛が細くないか、爪が脆かったり薄かったり、フラットだったりしないか、などをチェックします。
夜間に低血糖を起こしがちな人は、首肩周りのしつこい凝りや咬筋の緊張などがみられますし、ひどい場合には血糖値を上げるためにタンパク質が使われるので筋肉がつきにくくなったりします。
そういう人の脊柱起立筋は千歳飴みたいに硬い棒状になっていたりします。
体表所見から分かる栄養学的な情報って結構多くあるんです。
根本原因の類推
以上を総合的に判断して根本的な原因を類推します。
例えば慢性的な疲労感があってエネルギー産生が不足しているような場合、ATPをつくる代謝で必要になる栄養素(主にビタミンB群など)の不足をチェックします。
いくつかの問題点が混在していることはよくあります。
そういった場合には、根本原因を解決するためにどのような順序で治療を行なっていくかをよく検討します。
治療の順番を間違えると、治るまでの時間が長くなったり、治りにくくなったりするので、結構重要な問題なんです。
栄養アドバイス
まず大前提として、どのような食事スタイル(自炊中心・外食メイン・コンビニ中心など)かを尋ねます。
食事は誰がつくっているのか、好き嫌いがないかなどについても詳しく尋ねます。
好き嫌いが消化酵素の分泌低下や栄養素の不足によって起こっている場合などもよくあって、これはとても参考になる情報なんです。
さらに、治療の基本的な方向性として食事を中心にするのか、それともサプリも使って治療していくのかを確認します。
それらを踏まえて、食事および栄養アドバイスによって治していく順序を説明します。
問題点が複数あることも多いので、治していく順序が治療効果を左右するからです。
そしてやっと、当面(約3〜4ヶ月間くらい)の栄養アドバイスを詳細に行います。
次回のカウンセリングは3〜4ヶ月後に設定し、必要な場合は分子栄養学的にチェックするために必要となる項目で血液検査を実施してから受診してもらうようにします。
次を3〜4ヶ月後にするのにも理由があります。
まだ読んでない方は、こちらを参考にしてください。
そのときに、前回のアドバイスの方向性の確認や軌道修正などを行います。
患者さんの反応
患者さんも何となく食事は大切だと思っています。
ですからキチンと論理的に根拠を挙げてアドバイスをすると、よく聞いてくれます。
栄養不足から想定される症状などを指摘すると、栄養がそんなふうに様々な症状に影響していることに驚かれることは、よくあります。
初めからサプリを使うのではなく、小まめな食事指導を実践するだけでも、効果を感じてくれるようになることが多くあります。
すると逆に患者さんの方から「こういう場合はどうしたらいいでしょう?」などと質問してくれるようになるので、こうなればシメたものです。
人によっては、分からないことをいろいろと調べてきて僕に確認することを繰り返し、ほとんどご自分で解決できるようになる方もいるくらいです。
栄養療法の効果とメリット
僕は鍼灸師なので鍼灸と分子栄養学で患者さんを治しています。
栄養療法を根拠をもって使えるようになって、とても治療効果が上がるようになりました。
何より、鍼灸の臨床との相性がとてもいいと感じています。
皆さんもぜひ、ご自分の臨床に導入してみてください!
僕が分子栄養学と鍼灸治療を掛け合わせて行なっている臨床スタイルは、こんな感じです。
何となくイメージしてもらえたでしょうか?
これだけではちょっと伝え足りないし、少しでも多くの方に分子栄養学の必要性やメリットを正しく知ってもらいたいので、3月に「分子栄養学無料勉強会」下記の日時で開催することにしました。
- 3/7(金)20:00〜22:00
- 3/8(土)13:00〜15:00
無料ですので気軽に参加してほしいんですけど、2時間くらいシッカリと勉強しますので、それなりの覚悟(笑)で申し込んでください!
顔出しは必須で、寝てたらチョーク投げたり暴れたりします(ウソです 笑)
申込フォームはメールでお送りしますので、もうしばらくお待ちください。
では、今回はこの辺で。
分子栄養学に興味がある人はこちらをチェックしてみてください。
無料勉強会の最後に新しいセミナーについてもご紹介します。
僕の栄養療法外来はこちら。