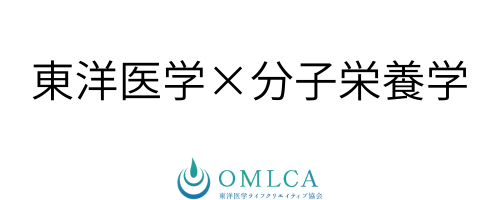前回は「鍼灸師の僕が分子栄養学を学んだ理由」について書きました。
皆さんも興味を持っていただけましたか?
僕はこのノウハウを鍼灸師や他のセラピストに広めたいと思っているので、今年はそのために動くつもりです(笑)
今回は僕のセミナーでしかやっていないことについて書きます。
セミナーに興味がない方も、東洋医学と分子栄養学の関係について僕が普段から考えていることを書きますので、読み進めてもらえると嬉しいです。
ブログの最後に、前回お約束した「分子栄養学無料勉強会」の日程のご案内もあります。
材料がないとダメ
前回、東洋医学と分子栄養学を掛け合わせるとすごく効果があるということを書きました。
今回はその部分をもう少し細かく書いていきます。
東洋医学では弁証をします。
これは四診によって得た情報を総合的に判断して患者さんのいまの状態を診断するという行為です。
例えば気血津液の状態でいえば、気の流れが悪いとか、血が足りないとかということですね。
この情報を元に治療方針を決めます。
気の流れが悪いのなら「気の流れを良くする」ですし、血が足りなければ「血を補う」になります。
でもちょっと考えてみてください。
何も材料がなくて血をつくるってどうやるんでしょうか?
これって、血の材料になる食事のアドバイスが必須じゃないでしょうか?
もちろん鍼灸を使って、血をつくるのに関係する臓腑の状態を良くすることはできます。
でも材料がなければ十分につくるのは難しいですよね。
仙人じゃないので、霞を食べて生きるわけにはいきません(笑)
材料はもちろん「食べたもの」
だから食事の指導が大事なんです。
血をつくるってことで言えば、赤血球も白血球もタンパク質でできていますし、ヘモグロビンには鉄が必要です。
血液は液体ですから、適度な水の補給もしてもらいたいです。
血液が中を流れる血管が脆いと困るので、丈夫な血管をつくるためにはコラーゲンの材料のタンパク質、鉄、ビタミンCが必須。
だから、これらが多く含まれる食材を摂るようにアドバイスします。
もちろん薬膳を使っても構いませんが、僕には分子栄養学が使いやすく感じたので愛用しています。
東洋医学はやっぱりスゴイ
変な話ですけど、分子栄養学を勉強してると、「やっぱり東洋医学ってスゴイなぁ」と思うことがちょくちょくあります。
血に関係したことでいうと、血の流れが悪い状態の「血瘀」という病態があります。
ちょっと考えても、血の流れが悪くなる理由っていろいろ思いつきますよね。
血が少ないとか、血がドロドロとか、心臓が血を送り出す力が弱いとか、血管の内側がボロボロで血が流れにくいとか…。
でもたぶん、東洋医学の血瘀という考え方には「血管が脆い」という概念も含まれていると思うんです。
血瘀のときに、青タンができやすくなるなんて書いてありますから。
これって分子栄養学的にいうと、壊血病の初期の段階のことです(僕は勝手に「プチ壊血病」って呼んでます)。
これを血瘀という病態に含めているって、やっぱりスゴいですよね。
面白すぎます!
僕の「東洋医学×分子栄養学」セミナーでしかやっていないこと
やっと今回の本題に入ります(笑)
あるとき、以前教えていた鍼灸学校の教え子さんが僕のセミナーに来てくれたんです。
その彼にどうして受講しようと思ったのかを聞いてみたら、彼が言っていたのは「分子栄養学に興味を持ってあるセミナーを受講して学んだんですけど、鍼灸の臨床にどう使っていいかまったく分からないでいたんです。そうしたら島田先生が分子栄養学のセミナーをやると知って、きっとその辺りを教えてもらえるはずだと思って来ました」とのこと。
彼は、はるばる群馬から泊まりがけで来てくれたんです。
そうなんですよ。
東洋医学と掛け合わせてどう使うかは、他のセミナーでは教えていないですし、僕自信いろいろと試行錯誤して組み立てて来たわけなので、そこが僕のセミナーの特徴でもあるんです。
ですから、東洋医学の気血津液弁証と分子栄養学的にみたいろいろな病態との関係性とか、脈や舌と栄養との関係とか、体表観察から得られる栄養不足やその原因など、そういった臨床での使い方をお伝えすることができるようになってきたと思っています。
先ほどの教え子の彼は、2日間10時間の基礎セミナーを受けた後に、こう言ってくれました。
「先生、臨床でこうやって使えばいいんだって、よくわかりました」。
すごく嬉しかったのをいまでも覚えています。
こういうときに、セミナーをやっていたよかったなぁって思うんです。
では、今回はこの辺で。
そうそう、前回のブログでお約束していた「分子栄養学無料勉強会」の日程が決まったのでお知らせしますね。2回やります!
- 3月7日(金)20:00〜22:00
- 3月8日(土)13:00〜15:00
興味のある方は、どちらかの時間を確保しておいてください。
ちなみにお申し込みは2/12(水)〜3/2(日)ですので、次回のブログでお知らせします。