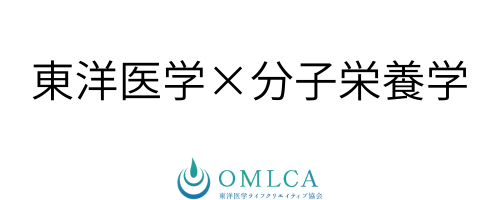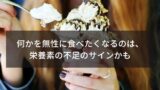皆さんは「日本人の食事摂取基準」というのをご存知でしょうか?
厚労省が国民の健康の保持・増進を目的として、5年ごとに定めているものです。
最新版は4月から5年間使用される2025年版。
もう出来上がっているので、厚労省のサイトにいくと概要をみることができます。
これって国の基準なので、栄養に携わる者にとっては大事な目安です。
Amazonで予約購入したんですけど、まだ手元には来ていません(笑)が、今回の改訂では少し見直されたところがあるようなので、その辺りについて書いてみようと思います。
日本人の食事摂取基準について
2025年版は、2023年度までに得られた科学的知見に基づいたものです。
この基準は、栄養に関する国内外の最新の知見や各種の診療ガイドラインの改定内容などを参照にしつつ、科学的な検討を重ねてつくられます。
内容としては、エネルギーと栄養素の摂取量の基準が示されされています。
僕も改訂のたびに購入して、必要に応じて目を通すようにしています。
2025年版の改訂ポイント
今回の改訂の主な変更点とされるのは、以下のとおりです。
- 食塩(Na)の目標量が0.5g/日引き下げられ、高血圧や慢性腎臓病の重症化予防を目的とした量として6g/日未満が設定された
- コレステロールの目標量が、脂質異常症の重症化予防を目的として200mg/日未満に留めることが望ましいとされた
- 飽和脂肪酸の目標量が、総摂取エネルギーの7%相当以下とされた
- 食物繊維の推奨摂取量が、従来の基準よりも1グラム増加し、1日当たり25グラム以上に変更された
- ビタミンDの推奨摂取量が、18歳以上の男女の目安量が9.0μg/日と設定された
- これまで成人男性で1日あたり45mg、成人女性で40mgとされていた鉄の耐容上限量が削除されました
- 鉄の栄養状態をみる指標として「フェリチン値」が推奨された
- ベジファーストの項目が削除された
いくつかについて、私の考えなどを織り交ぜて書いていきます。
食塩について
これは前回のブログ記事にも書いたので繰り返しになりますが、質の良い海水からつくった塩と工場で精製してつくられたNacl(塩化ナトリウム)とでは、カラダに対する作用がまったく違います。
ナトリウムだけを大量に摂れば、栄養学的にみてもカラダに悪いのは歴然としています。
もちろん血圧も上がりやすくなるはずです。
その理由は、ミネラルというのはバランスがとても大事だからです。
たとえばナトリウムは、カリウムとの摂取バランス。
海水からつくった質の良い塩には、さまざまなミネラルが含まれているので、ちょっとぐらい多めに摂っても血圧が高くなることはあまりありません。
逆に高血圧の人は、カリウムを積極的に摂ると血圧が下がる場合が多いんです。
そもそも塩分の摂取で血圧が上がるタイプ(食塩感受性高血圧)の割合は、日本人では高血圧のうち40%程度だと言われているのをご存知でしょうか?
これは遺伝的な要因が大きいともされているので、両親が高血圧の場合に可能性が高いかもしれませんが、それ以外の人はあまり塩分摂取を気にすることがないということにもなります。
そういう意味でも、塩の摂取を制限するよりは、良い塩を使うことのほうが大事だと思います。
コレステロールについて
食事によるコレステロールの摂取は血中のコレステロール値に直接的に影響を与えないことから、コレステロールの摂取量の基準値は定められていませんが、2020年版からは、脂質異常症の重症化予防を目的としてコレステロールを200mg/日未満に留めることが望ましいとされていました。
基本的にその方針が今回も踏襲されたようです。
コレステロールは卵、肉、魚などの動物性たんぱく質を多く含む食品に含まれているため、特に高齢者では、コレステロールの摂取量を制限しようとするとたんぱく質不足を生じやすく、その結果として低栄養を生じる可能性があるため、そういう意味での注意が必要だと思います。
食物繊維について
食物繊維の推奨摂取量の基準値が1日1g増えました。
これは、生活習慣病のリスク低下に寄与することが明らかになったためです。
以前調べたことがあるんですけど、20代の女性の足りていない栄養素トップ5に食物繊維が入っていたんです。
食物繊維の効果はかなり大きいので、腸内環境のためには是非しっかり摂りたいですね。
ただし、食物繊維といわれて想像するのは繊維質が多そうな野菜じゃないですか?
それは不溶性の食物繊維。
じつは食物繊維には水に溶けにくい不溶性と溶けやすい水溶性があることを知っておきましょう。
そして、水溶性の食物繊維をしっかり摂ることがとても大事です。
水溶性食物繊維は水に溶けてドロドロになり、胃や小腸、大腸の中で一緒に食べた物の粘性を高めます。
これによって、栄養素の消化・吸収を緩やかにし、食後の血糖値の上昇を抑えると考えられています。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の割合は1:2になるよう摂取するのが理想的だとされています。
水溶性食物繊維が多く含まれる食品は、野菜類ではアシタバや春菊、カボチャなど、いも類ではサツマイモなど、果物ではミカン、キウイなど、海藻類ではのりやわかめ、昆布などです。
不溶性食物繊維を多く含む食品は、野菜、豆類、果物、きのこ類、穀類などです。
お通じという意味でざっくり言うと、不溶性は便の量、水溶性は便の出やすさに関係するといっていいと思います。
ビタミンDについて
ビタミンDの摂取量を増やすのも良いことだと思います。
以前はこのビタミン、骨を強くする作用があると言われていました。
ですが現在ではさまざまな効果がわかってきていて、ホルモンのようだとまで言われるようになりました。
妊活のときにもある程度上がらないとダメだと言われていますし、いろいろながんの予防効果もあることが報告されています。
花粉症にも効果がありますし、炎症を抑えてくれる効果まであります。
サプリも安いですから、気軽に補給することができるんですけど、その場合にはいくつか問題になることがあります。
ひとつめは大量に摂取すると過剰症になる可能性があることです。
それを防ぐためには、ビタミンKを一緒に摂ることが必要です。
海外のサプリでは、D&Kという形になっているものが多いので、そういうものを選びましょう。
あとひとつは、脂溶性のビタミンなので油の吸収が悪い人は血中濃度が上がってきません。
サプリで摂っていても血液検査で測ると血中濃度が低いままの人が結構います。
そういう場合は、脂質の吸収を改善する必要があるんです。
基本的にビタミンDは日に当たることで皮下のコレステロールを材料につくることができます。
日焼けするほど日に当たる必要はありませんが、適度に日には当たるようにしてください。
現代人は「高カロリー栄養失調」状態にあるといわれます。
そういう意味で、カロリーを控えめにして、ビタミンとミネラルを積極的に食品から摂るように心がけるべきです。
鉄の耐容上限量の削除
これまで成人男性で1日あたり45mg、成人女性で40mgとされていた鉄の耐容上限量が削除されました。
鉄は体内で重要な役割を果たす微量ミネラルで、特に赤血球の生成に欠くことのできない大切な栄養素です。
従来は、鉄による健康障害を防ぐための摂取量の上限として耐容上限量が設定されていました。
しかし、近年の研究により、鉄の過剰摂取がもたらす影響についての理解が深まってきました。
特に、以下の点について明らかになってきています。
- 食事からの鉄摂取量が多くても、体内での調整機能が働くこと
- 遺伝的要因の関与がある場合を除いて、過剰障害のリスクはある程度無視できること
- 個々の健康状態に応じて必要量が異なることが判明したこと
これらの認識の変更により、特に高齢者や女性において、より柔軟な栄養管理が可能になってくると思われます。
ただし、これは無制限な摂取を推奨するものではないんです。
鉄分の過剰摂取によって体内での酸化ストレスが引き起こされ、そのことによるさまざまな臓器障害のリスクを高める可能性もあります。
健康状態や生活状況に応じた個別性を考慮した適切な摂取が大事です。
かなり長くなってしましましたが、今回はこの辺りで。
4月から新しく「3ヶ月栄養カウンセリングオンラインセミナー」を開講します。
栄養カウンセリングができるようになることに特化した実践型のセミナーです。
お申し込みは3/31までです。
興味のある方は下記のボタンから詳細ページをご覧ください。